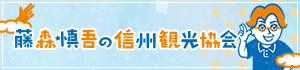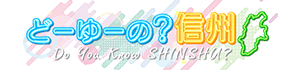いいね!信州スゴヂカラ
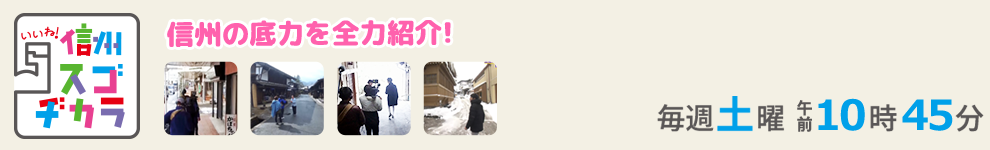
放送内容
秋の風物詩!佐久市の田ブナを探る

佐久市に伝わるフナの水田養殖。収穫されるフナは田ブナと呼ばれ、秋の味覚として珍重されています。今回、田ブナにまつわるスゴヂカラを探ります。

佐久市の臼田節雄さんの田んぼでは毎年9月にフナの収穫をしています。フナを飼うことで農薬の使用を減らすことができ、また、フナが動き回ることで水が濁り雑草の繁殖を抑えてくれるのだそうです。さらに、穫れた米はフナ米として高値が付きます。しかし、担い手不足は深刻で、2006年に147あったこの地域の生産農家は2020年には47に減りました。

フナの収穫は田んぼの水を払い、溝を掘りフナの通り道を作ります。そこに少量の水を流すと、フナはそれに向かって上ってきます。自然の仕組みとは不思議なものです。臼田家では二人の孫が収穫の手伝いをすることもしばしば。家族総出で泥だらけになってフナを追う…という風景はかつてこのあたりで多く見られたんだそう。生産農家ならではのフナの甘露煮とフナ米の味は絶品です。

フナは地元のJAに出荷され秋の味覚として販売。その後各家庭で調理されます。定番は甘露煮ですが、佐久市の関ゆり子さんのお宅では、背開きにして唐揚げにすることも多いとか。素揚げに塩を振り、また、甘醤油にさっと通していただくそうです。佐久市の伝統的食文化に触れます。
秋の風物詩!田ブナって何だ?
珍重!食文化 フナの水田養殖
[珍]活ブナ!待ち焦がれる人々
取材情報
- JAさく南部営農センター
TEL:0267-62-8145