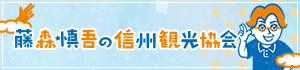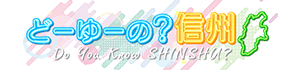いいね!信州スゴヂカラ
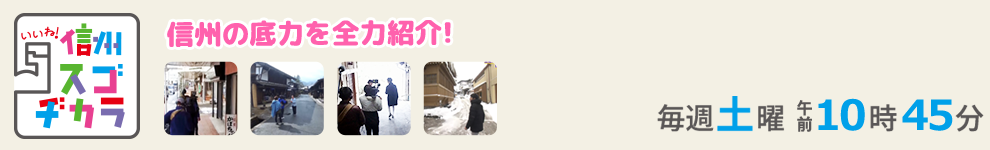
放送内容
木曽漆器 ~伝統の世界に新しい風~

塩尻市・木曽平沢は漆器の里。町のメイン通りには約100の漆器店が並び、椀や箸、器、家具など様々な漆器を扱っています。
毎年6月、通りを歩行者天国にして店頭に漆器を並べて売る「木曽漆器祭」が開かれます。今年で52回目を迎え、お目当てのものを探す熱心な客が県内外からやってきます。漆器祭では、見た目はわからないほどの傷があるお値打ち品や掘り出し物、蔵出し品を探す楽しみがあります。気に入った品を見つけ、店の人と値段交渉するのも恒例の光景です。
毎年6月、通りを歩行者天国にして店頭に漆器を並べて売る「木曽漆器祭」が開かれます。今年で52回目を迎え、お目当てのものを探す熱心な客が県内外からやってきます。漆器祭では、見た目はわからないほどの傷があるお値打ち品や掘り出し物、蔵出し品を探す楽しみがあります。気に入った品を見つけ、店の人と値段交渉するのも恒例の光景です。
萩原アナは祭りに参加するのは初めて。木曽平沢を訪ねて、漆器に対するイメージが変わりました。普段あまり使わない盆や椀が一般的で、若い人向けではないちょっと高級品。しかも扱いづらいという印象を持っていました。しかし今、新しい素材を使った漆器が登場し、若い世代にも浸透しているのです。ガラス、革、金属、陶器などの美しく、使い勝手の良い漆器。いずれも木と違って漆がはがれやすい難点がありましたが、独自の技術で道を切り開きました。若い職人が担っているのも特徴です。
中には、内装も外装も総漆塗りという乗用車もあります。木曽漆器をPRするために造ったもので、もちろん公道を走れます。
中には、内装も外装も総漆塗りという乗用車もあります。木曽漆器をPRするために造ったもので、もちろん公道を走れます。




もともと漆は接着剤や塗料として古くから使われてきました。壁や床などに塗って、耐水性を高める役割もあります。食卓や部屋から漆器が姿を消しつつある中、萩原アナは、新しい木曽漆器を生み出す工房を訪ね、完成に至る苦労や、若い担い手を知り、漆器の魅力・可能性に触れます。
重要伝統的建造物群保存地区になっている木曽平沢の「漆工町」の木造の町並みも見どころです。

取材先情報
- 木曽くらしの工芸館
TEL:0264-34-3888
- 本山漆器店
TEL:0264-34-2511
- 伊藤寛司商店
TEL:0264-34-2034
- 丸嘉小坂漆器店
TEL:0264-34-2245(漆硝子)
- 未空うるし工芸
TEL:0264-34-2644(革製品)