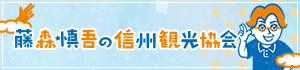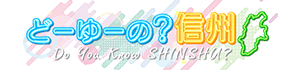いいね!信州スゴヂカラ
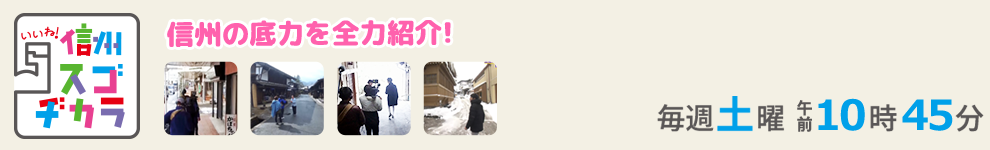
放送内容
肥沃の大地!善光寺平で″島″探し

長野市内には島の付く地名がたくさんあります。川中島、青木島、丹波島、綱島、大豆島など。しかし、なぜ、これらの地名に「島」が付いているのでしょうか。そこで今回は、善光寺平で「島」を探します。
楠原アナウンサーが県立長野図書館で見つけた更級郡誌によると、平安時代の終わりに、犀川の氾濫でできた3つの島を「川中島」と呼んだとあります。長野市の「島」の生い立ちは、どうやら「川」が影響しているようです。屋島と小島の間にある柳原で、地質発掘調査の現場に遭遇。調査員から地質図なるものを見せてもらうと、そこにはたくさんの島状の地形が記されています。
地質図から、千曲川と犀川の流れが、長い年月をかけ長野市内の島地形をつくったことがわかります。松代町では「三郡境(さんぐんざかい)の石」にたどり着きます。その昔この場所は更級郡、高井郡、埴科郡との境でした。かつての郡境は、山や川などによって分かれていました。この石の近くに千曲川が流れていたそうです。大室地区では、大室古墳群から多くの馬具が出土していることから、この近くでたくさんの馬や牛が飼われていたとされます。そして、馬島が真島、牧場の島で牧島、牛島はそのまま牛島、というように島の名が付けられたそうです。牧島は、かつて千曲川が大きくカーブして流れていた場所で、上空から見ると、島の部分に民家が集中しているのがわかります。また、千曲川の氾濫がつくった三日月湖の金井池や、長野南高等学校の近くに残る、旧犀川の土手などを訪れます。




取材先情報
- 川中島古戦場
TEL:026−224−5054
(長野市公園緑地課)
- 長野県埋蔵文化財センター
TEL:026−293−5926
- 大室古墳群
TEL:026−284−0004
(長野市教育委員会)
- 長澤果樹園
TEL:026−284−1867