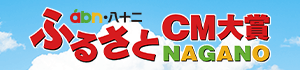新聞に乗らない内緒話
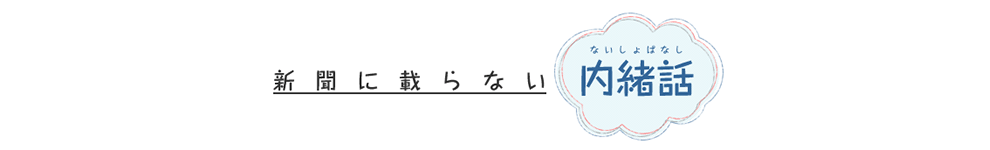
コラム
実りの行方
五穀豊穣(ほうじょう)を神々に謝する秋祭り。秋晴れの陽射しの中、旅先で訪れた小村、町でふいに出くわすことがある。
10月は実りの季節ではあるけれど、一方でその余得からも見放された、貧しい農婦たちを描く「落ち穂拾い」をご記憶であろうか。
フランスの画家・ミレーの代表作とされ1857年に描かれた。パリ郊外の都市フォンテーヌブローの森のはずれにある、シャイイの農場が風景となっている。
学校の、美術の教科書で一度はお目にかかっているはずの1枚である。
当時の、フランスの農場では収穫を終えた畑の落ち穂をわざと残す習いがあった。少量の穀物からも見放された人たちへの思いやり、救済をさりげなく含ませたのであろう。
旧約聖書に「穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者(旅人)のために残しておかねばならない」とある。
日本にもかつて、似たような風景があった。
収穫を終えた柿の木に、ひとつだけ柿の実を残した。 これを木守柿(きもりがき・こもりがき)、あるいは木守と呼んだ。
今年もたくさんの実をつけた木をねぎらい、来年の収穫を祈るのである。そして、たったひとつの柿は冬を目前にした鳥たちの、食料として供された。
かつての農村では嫁入りにあたって実家から柿の苗を持って行き、それを嫁ぎ先に植えたという。その実は生前、山里の糧(かて)として温存され、嫁が生涯を終えると、大きく育った柿の枝が火葬の薪(まき)や、骨を拾う箸にされた。
「つまり柿は、女性の生涯を象徴する木だった」と書いたのは「秋日和」の坪内稔典であった。
「芭蕉の句に~里古(ふ)りて柿の木持たぬ家もなし~という故郷の伊賀上野での句があるが、古い村の家々の柿の木は、代々の嫁が残したものに違いない」と付け加えている。
もっとも最近は、たわわに実った柿が収穫されることもなく晩秋の残景になっている。夕陽を真っ向から照り返す赤が、いつか赤銅色にくすんで、そしてボタリと地に落ちた。
渋柿ならヘタに焼酎を付け渋抜きし食料として冬に備えた。干し柿にもなった。高所に成(な)ったそれは竿を二又に割って、枝を挟み込んで収穫した。
その手間暇を掛けるだけの人々が、今は居ない。鳥、猿たちがが存分に豊穣の分け前にありついている。
(日刊スポーツ I / 2019年10月)
★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで