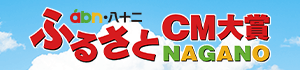新聞に乗らない内緒話
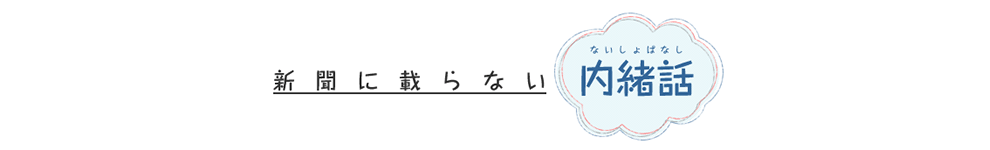
コラム
孤独と孤立
定年で会社員生活も終了、消滅した習慣はいくつもあるが、そのひとつに通勤がある。帰り道、酒場に寄って「ちょいと一杯」が楽しみだった。
新聞社も、もちろん組織で動いているが、その勤務はまだら模様で自分の仕事にメドがつけばそれが終業時間となる(取材部門での話だが)。個人の判断に委ねられる領域が広い。書いた記事、取材に予断があれば対応も必要だが、それも自己判断である。
時間が不規則で、それも深夜が絡むから通常の友人と気軽に飲むことは難しい。同僚はいるが、これも自己判断で動いているから「軽く一杯」と誘うタイミングが難しい。
「独り飲み」がどうしても日常化する。頭の中はまだ仕事の余韻が残っており、ガサガサしているからその揺らぎを自宅には持ち帰りたくない。精神の緩衝材として酒場が存在してる。
行きつけの、顔見知りの居る酒場ならば結構だが、それも余り親しくなって余計な会話も時には煩わしい。ということで注文さえ受ければ後はほったらかしにしてくれる居酒屋チェーン店のカウンターが止まり木となる。「独り飲みって難しいでしょう。何だか落ち着かないし」とよく人に尋ねられるが、私に限って言えば何ら不都合はない。
読みかけの本を持ち込むことあるし、周辺の会話に耳を傾け記事を書くヒントを貰った。些細なきっかけで時には友人もできる。冷や酒二杯、肴一品で早々に引き揚げる。長居は無用、いつでも腰を上げられるのが有り難い。
先日、朝日新聞の別冊でこんな記事を見かけた。「単独の食事で何が悪い!実は心地よい『ひとりメシ』」。筆者はマイケル・ブースという英国生まれのジャーナリストとあり、著書に「英国一家、日本を食べる」(読んだ記憶がある。食事風景文化論であろうか)などを持つ知日派である。
この御仁、「仕事のために外食することが多い」そうだが、例えば韓国では「1人での食事は成立しない」という。「店に入ってあいていますかと聞くたびに、店員はいつも『で、お連れ様は?』とでも言わんばかりに私の肩越しに目をやるのだ」。イタリアでは「町の食堂の薄暗い隅っこやトイレのそばで、または入口から来る冷たい風の中で忘れられ」「立ち上がって店員の正面で自分の存在を思い出させなければならない」そうだ。
その国の社交性を物語るエピソードだが、日本の飲食店はどうだろう。相席も含め「独り」を露骨に拒むことはない(例外はあるが)。常設されるカウンター席は日本ならではの食空間、飲食文化とも言えるのではないか。
背中を丸め、杯をあおる。その寂寥を嫌がる風潮にも変化が見える。「独り飲み」の格好良さが強調される時代だ。孤独と孤立は違う。自分の意思で孤独を楽しみたい。孤立しないために、カウンターの隣人にふと声を掛けてもみたい。酒場は、そうあって欲しい。
新聞社も、もちろん組織で動いているが、その勤務はまだら模様で自分の仕事にメドがつけばそれが終業時間となる(取材部門での話だが)。個人の判断に委ねられる領域が広い。書いた記事、取材に予断があれば対応も必要だが、それも自己判断である。
時間が不規則で、それも深夜が絡むから通常の友人と気軽に飲むことは難しい。同僚はいるが、これも自己判断で動いているから「軽く一杯」と誘うタイミングが難しい。
「独り飲み」がどうしても日常化する。頭の中はまだ仕事の余韻が残っており、ガサガサしているからその揺らぎを自宅には持ち帰りたくない。精神の緩衝材として酒場が存在してる。
行きつけの、顔見知りの居る酒場ならば結構だが、それも余り親しくなって余計な会話も時には煩わしい。ということで注文さえ受ければ後はほったらかしにしてくれる居酒屋チェーン店のカウンターが止まり木となる。「独り飲みって難しいでしょう。何だか落ち着かないし」とよく人に尋ねられるが、私に限って言えば何ら不都合はない。
読みかけの本を持ち込むことあるし、周辺の会話に耳を傾け記事を書くヒントを貰った。些細なきっかけで時には友人もできる。冷や酒二杯、肴一品で早々に引き揚げる。長居は無用、いつでも腰を上げられるのが有り難い。
先日、朝日新聞の別冊でこんな記事を見かけた。「単独の食事で何が悪い!実は心地よい『ひとりメシ』」。筆者はマイケル・ブースという英国生まれのジャーナリストとあり、著書に「英国一家、日本を食べる」(読んだ記憶がある。食事風景文化論であろうか)などを持つ知日派である。
この御仁、「仕事のために外食することが多い」そうだが、例えば韓国では「1人での食事は成立しない」という。「店に入ってあいていますかと聞くたびに、店員はいつも『で、お連れ様は?』とでも言わんばかりに私の肩越しに目をやるのだ」。イタリアでは「町の食堂の薄暗い隅っこやトイレのそばで、または入口から来る冷たい風の中で忘れられ」「立ち上がって店員の正面で自分の存在を思い出させなければならない」そうだ。
その国の社交性を物語るエピソードだが、日本の飲食店はどうだろう。相席も含め「独り」を露骨に拒むことはない(例外はあるが)。常設されるカウンター席は日本ならではの食空間、飲食文化とも言えるのではないか。
背中を丸め、杯をあおる。その寂寥を嫌がる風潮にも変化が見える。「独り飲み」の格好良さが強調される時代だ。孤独と孤立は違う。自分の意思で孤独を楽しみたい。孤立しないために、カウンターの隣人にふと声を掛けてもみたい。酒場は、そうあって欲しい。
(日刊スポーツ I / 2020年3月)
★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで