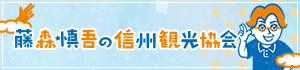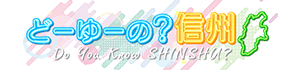新聞に乗らない内緒話
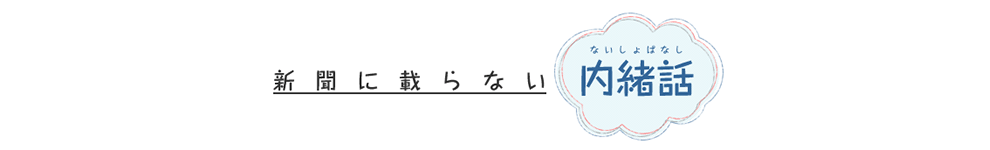
コラム
五輪〝名言〟異聞
オリンピック・イヤーの幕開けである。
「参加することに意義がある」という〝名言〟を思い出す方も多かろう。もっとも商業主義のはびこる近年の大会で「とりえず参加を」など呑気なことを言い出せば顰蹙(ひんしゅく)を買うだけだろう。
メダルには競技場内外の、あらゆる思惑、欲が絡んでいる。勝ってナンボなのである。
さて前述の〝名言〟「参加することに意義がある」は、IOC第2代会長・ピエール・ド・クーベルタンの言葉と思い込んでいた。間違いであった。浅学の極みである。
説明には1908年、ロンドンで開催された第4回大会まで遡る必要がある。
オリンピック参加が国別となった初めての大会で、開会式でのアルファベット順、国旗を掲げての入場行進が採用されている。だからであろうか。ナショナリズムの台頭、誇示するムードが目立つ大会であったという。とりわけ急成長著しい米国選手団は、開会式で国旗が掲揚されなかったことから英国王への欠礼を露骨にするなどスポーツ宗主国、特に英国への反感、さらに過度の国威高揚、競争をあからさまにした。
例えば陸上400㍍決勝、米国選手のファウルの判定を不服とし、他の米国決勝進出選手の出場をボイコットするなど荒れ模様で、クーベルタンの言葉を借りれば「野蛮極まりない(米国選手の)叫び声がスタジアム中に響き渡」る状況であったらしい。
「参加することに意義がある」という〝名言〟を思い出す方も多かろう。もっとも商業主義のはびこる近年の大会で「とりえず参加を」など呑気なことを言い出せば顰蹙(ひんしゅく)を買うだけだろう。
メダルには競技場内外の、あらゆる思惑、欲が絡んでいる。勝ってナンボなのである。
さて前述の〝名言〟「参加することに意義がある」は、IOC第2代会長・ピエール・ド・クーベルタンの言葉と思い込んでいた。間違いであった。浅学の極みである。
説明には1908年、ロンドンで開催された第4回大会まで遡る必要がある。
オリンピック参加が国別となった初めての大会で、開会式でのアルファベット順、国旗を掲げての入場行進が採用されている。だからであろうか。ナショナリズムの台頭、誇示するムードが目立つ大会であったという。とりわけ急成長著しい米国選手団は、開会式で国旗が掲揚されなかったことから英国王への欠礼を露骨にするなどスポーツ宗主国、特に英国への反感、さらに過度の国威高揚、競争をあからさまにした。
例えば陸上400㍍決勝、米国選手のファウルの判定を不服とし、他の米国決勝進出選手の出場をボイコットするなど荒れ模様で、クーベルタンの言葉を借りれば「野蛮極まりない(米国選手の)叫び声がスタジアム中に響き渡」る状況であったらしい。
◆
こんな険悪なムードを憂慮、米国から選手団に随行したペンシルベニア大司教エチュルバート・タルボットは自国選手たちに対し、こう強く諭した。
「オリンピックにおいて重要なのは勝利することよりむしろ参加したことであろう」。
クーベルタンはその言葉を聞きつけ、5日後に大会役員が集まるレセプションで以下のようにスピーチしている。
「ペンシルベニアの司教が述べられたのは、まことに至言である。人生において重要なことは、成功することではなく、努力することである。根本的なことは征服したかどうかにあるのではなく、よく闘ったかどうかにある。このような教えを広めることによって、いっそう強固な、いっそう激しい、しかもより慎重にして、より寛大な人間性を作り上げることができる」(「名言の正体 大人のやり直し偉人伝」山口智司著・学研新書)
クーベルタンが強調したかったのは「征服したかどうかにあるのではなく、よく闘ったかどうか」の部分であったはずだが、人々の記憶に残ったのは司教の、冒頭の「オリンピックにおいて重要なのは勝利することよりむしろ参加したことであろう」であった。
それが、引用者であるクーベルタンの〝名言〟として後世に残った。第10回ロサンゼルス大会以降の、選手娯楽室にはクーベルタンの「言葉」として掲げられたという。
(日刊スポーツ I / 2020年1月)
★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで