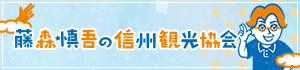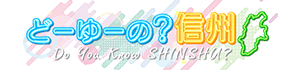新聞に乗らない内緒話
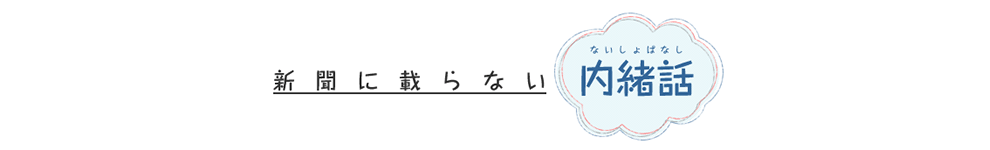
コラム
七味五楽三会
「一富士二鷹三茄子(なすび)」とは、縁起の良い初夢のこと。
富士は日本一の山、鷹は賢くて強い鳥、茄子は事を「成す」。徳川家康が好んだ富士山、鷹狩り、初物の茄子。他にも、江戸時代の富士講に由るとの説もある。
先日、この「一富士二鷹三茄子」を一度に味わってやろうと静岡市を訪ねた。頂戴したお弁当を開いたら、その片隅に煮付けた「茄子」が田楽風に鎮座していた(ついでに由比港に立ち寄り桜エビの沖漬け、かき揚げも賞味した。絶品である)。
久能山東照宮の唐門をくぐったら「二羽の鷹」を発見した。
あとは「一富士」だけである。世界文化遺産を構成する資産のひとつ、三保の松原へと赴いた。前日までの不順な天候も、この日は雲ひとつ無い、文字通りの日本晴れ。
海岸縁で、強烈な北風にあおられ、コートの襟はハタハタ鳴ったが、その見晴らしは絶景であった。紺碧の空、霊峰頂きにかかる雪、すそをあしらう万緑の松林。
三色一体。「まるで銭湯のペンキ絵。絵葉書そのものだね」と毒づいたら「地元のわたしらでもこんな富士山を見るのは今年初めて。ぜいたくをいうもんじゃない」とたしなめられた。
初春の吉兆である。「ありがたや」と手を合わせた。
「一富士二鷹三茄子」、その言葉のリズムの良さで人口に膾炙(かいしゃ)したのだろうが、そう言えばその昔、江戸の庶民は「七味五楽三会」と唱えたものだと江戸研究家の杉浦日向子さん(早世してしまったが)が話していた。略して「七五三」―。
「七味」とは、味を楽しむという意。昨今の、これ見よがしの高価なグルメではあるまい。旬の、フッと出合った小さな味、生活の味が1年に7回も舌上のぼれば本望、だそうだ。
「五楽」は「あぁ、今日は良い1日だった」という感慨。楽しい想い出が5回もあったらめっけもの、手のひらに乗るような幸せで十分だ。
「三会」はせめて3人の、〝友〟と巡り会いたい。親友などと大仰な事は言うまい。かすり傷のよう縁(えにし)でも、気持ちの良い人と話がしたいのである。
大晦日の夜に1年をふり返り、その年が「七味五楽三会」であったなら、「こんな目出てぇ年はないねぇ」と江戸の人は喜んだという。
ふり返れば、良くも悪くも諦念(ていねん)の似合う年回りとなった。すべて山っ気も、娑婆っ気も抜けたようである。色落ちがあったり切りっぱなしであったとしても、使い古しの、木綿の手拭いのようなしんなりと、肌になじんだ1年を送りたい。
「七五三」―。
脈拍数を落として生きよという、江戸からの伝言であろう。
(日刊スポーツ I)
★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで