新聞に乗らない内緒話
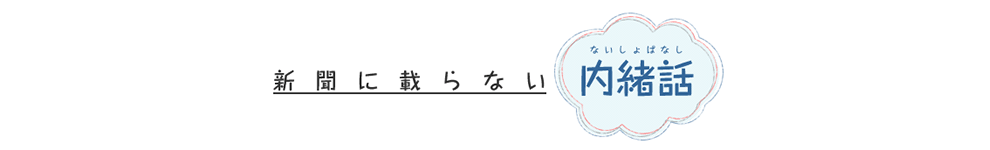
コラム
「8月15日」から
淡谷のり子。年配には「ブルースの女王」として言うまでもない。戦時中、軍歌、モンペを拒否、ドレスをまとい、禁止されたブルースで兵士たちを慰問し続けた「不屈」の人。
◆
(8月15日は)戦争というものの持つ狂騒音が、ぱったりと死に絶えて、新しい誕生を待つ夜明けの静けさのようであった。
三日目に、山形県庁の役人が宿屋にやって来た。
「進駐軍向けに、ショーを組んで、やって欲しいんですが」という。
今まで、さんざ、いじめぬいておいて、戦争に負けた途端に、今度は進駐するアメリカ兵のご機嫌取りに使うわけか。
私はその県庁の役人を使ってよこした、もっと上の、私どもには容易に見えない力に、皮肉なくくすぐったい気持ちを抑えることが出来なかった。
「何はともあれ、歌えるとあればありがたい」
私はすぐ、山形に疎開していた石井不二香さんと相談して、私のバンドと一緒に、方方の進駐軍のキャンプに出かけて行くことになった。
(淡谷のり子・わたしの八月十五日=山形巡業中。当時37歳=歌手=文芸春秋)
続いて沢村貞子。名脇役女優として活躍、NHK連続テレビ小説「おていちゃん」はご存じだろう。左翼演劇に感応し2度の逮捕を経て映画界にもデビュー、名随筆家としても名を残した「信念」の人。著書に「貝のうた」「私の浅草」等。
◆
とうとう、また生きのびた。戦争は終わった。日本は敗れた。何もかも、すべてがひっくり返るにちがいない。日本は、やりなおしだ。
〈……私も、もう一度やりなおすわけにはいかないであろうか―できれば、もう一度、生きなおしてみたい―まだ四十には間があるんだもの……〉
その夜、二階の、黒い覆いをとった電燈の下で、私はいつまでも、机に頬杖をついていた。
〈……いまさらやり直しても、どんな生き方をすればいいのかわからない。やっぱり、同じようなことしかできないかもしれない。……それでもいい、人を裏切らず、人に迷惑をかけず……生命の終わるまで、一生懸命生きてみたい……〉
(沢村貞子・わたしの八月十五日=終戦時・東京。当時36歳=女優)
そう自分に言って、聞かせて、踏ん切りをつけて、生きた。
(日刊スポーツ I / 2020年8月)
★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで







