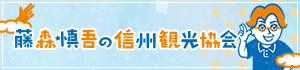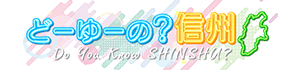新聞に乗らない内緒話
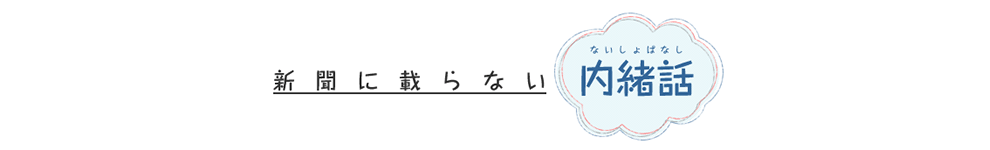
コラム
「赤い星」2題
独身寮管理人の仕事を終え、午後6時過ぎ帰路につく。道の傍らは、JRの巨大な操車場で京浜東北線車両が列を整えている。
この時刻、サラリーマンの帰宅ラッシュに対応するためであろう、構内の電車が高く警笛を鳴らし、車体を揺らしながら本線へ向け出発してゆく。車輪の軋む金属音はこの街の、一日の終わりを告げる〝晩鐘〟で、余談ながら松本清張原作の長編小説「砂の器」は、この操車場での殺人事件で幕を開ける。
さて今春であったか、西の空を見上げるとひときわ大きく、赤色に輝く物体がある。一瞬近くにあるタワーマンションの、航空障害灯かと思ったがすぐに気がついた。
火星、である。
1877年(明10)9月3日、この「赤い星」は地球に大接近する。人々の目にはさぞ大きく映ったことであろう。「西南珍聞」という木版画には人々が物干し台に昇り、望遠鏡で観察する様子が描かれている。浴衣にちょんまげ、丸髷(まるまげ)姿が天を仰いでいる。維新から10年経っても、庶民の風俗はどうも旧態依然である。
それはさておき人々はこの巨星を「炎(ほのお)星」、もしくは不気味な赤色ゆえ「災い星」と呼んでいたのだが、この年ばかりは違った。「西郷星」と命名したのである。
9月24日は西郷隆盛の命日。1877年(明10)の西南戦争で、官軍の包囲を受け自決している。「西鄕さんが、死んで星になった」と庶民はそう考えた。星の中に軍服姿を見いだしたのであろうか。
もうひとつ。「赤い星」といえばこんな話がある。1582年(天正10)5月、京都、安土(あづち)上空で赤い、光り物が確認された。彗星(すいせい)、大流星、火球と呼ばれたが、人々はそれを凶兆とし、おののいた。
安土(現滋賀県近江八幡市)といえば「天下布武(てんかふぶ)」を唱え、武力による統一を目指した織田信長の居城・安土城を思い出す。琵琶湖に岬のように突き出た小山に目を付け、1576年(天正4)に築城を始めている。
城郭が整い、2年後には天主(天守ではない)が完成している。高い石垣、五重六階。黒漆塗りの下層に加え、上層の天主は不等辺八角形で朱塗りの柱、壁には彫刻をほどこす絢爛ぶりで、金色に光ったといわれる。城下はご存じ「楽市楽座」、通商の便宜が図られ賑わったのは言うまでもない。
その城も完成から僅か3年後、つまり「赤星」の出現した年に姿を消す。
本能寺の変で信長は非業の死を遂げ、安土城はその数日後、何者かの放った火によって炎上、一部を残し焼け落ちている。
2年後、羽柴(豊臣)秀吉はこの城を廃城とした。ゆえ「幻の名城」と呼ばれる。
この時刻、サラリーマンの帰宅ラッシュに対応するためであろう、構内の電車が高く警笛を鳴らし、車体を揺らしながら本線へ向け出発してゆく。車輪の軋む金属音はこの街の、一日の終わりを告げる〝晩鐘〟で、余談ながら松本清張原作の長編小説「砂の器」は、この操車場での殺人事件で幕を開ける。
さて今春であったか、西の空を見上げるとひときわ大きく、赤色に輝く物体がある。一瞬近くにあるタワーマンションの、航空障害灯かと思ったがすぐに気がついた。
火星、である。
1877年(明10)9月3日、この「赤い星」は地球に大接近する。人々の目にはさぞ大きく映ったことであろう。「西南珍聞」という木版画には人々が物干し台に昇り、望遠鏡で観察する様子が描かれている。浴衣にちょんまげ、丸髷(まるまげ)姿が天を仰いでいる。維新から10年経っても、庶民の風俗はどうも旧態依然である。
それはさておき人々はこの巨星を「炎(ほのお)星」、もしくは不気味な赤色ゆえ「災い星」と呼んでいたのだが、この年ばかりは違った。「西郷星」と命名したのである。
9月24日は西郷隆盛の命日。1877年(明10)の西南戦争で、官軍の包囲を受け自決している。「西鄕さんが、死んで星になった」と庶民はそう考えた。星の中に軍服姿を見いだしたのであろうか。
もうひとつ。「赤い星」といえばこんな話がある。1582年(天正10)5月、京都、安土(あづち)上空で赤い、光り物が確認された。彗星(すいせい)、大流星、火球と呼ばれたが、人々はそれを凶兆とし、おののいた。
安土(現滋賀県近江八幡市)といえば「天下布武(てんかふぶ)」を唱え、武力による統一を目指した織田信長の居城・安土城を思い出す。琵琶湖に岬のように突き出た小山に目を付け、1576年(天正4)に築城を始めている。
城郭が整い、2年後には天主(天守ではない)が完成している。高い石垣、五重六階。黒漆塗りの下層に加え、上層の天主は不等辺八角形で朱塗りの柱、壁には彫刻をほどこす絢爛ぶりで、金色に光ったといわれる。城下はご存じ「楽市楽座」、通商の便宜が図られ賑わったのは言うまでもない。
その城も完成から僅か3年後、つまり「赤星」の出現した年に姿を消す。
本能寺の変で信長は非業の死を遂げ、安土城はその数日後、何者かの放った火によって炎上、一部を残し焼け落ちている。
2年後、羽柴(豊臣)秀吉はこの城を廃城とした。ゆえ「幻の名城」と呼ばれる。
(日刊スポーツ I / 2020年9月)
★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで