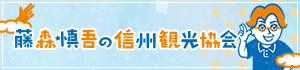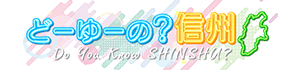新聞に乗らない内緒話
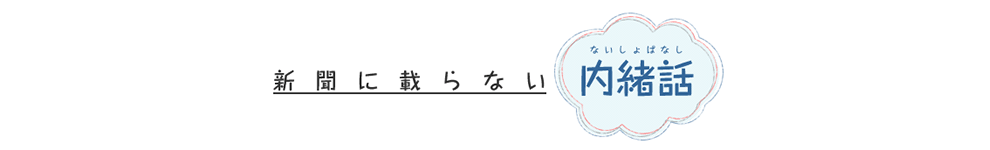
コラム
「夢」の裏付け
1964年(昭39)10月10日、東京五輪が開幕した。
当時小学校5年生であった。開幕日が近づくと、父親があたふたと商店街の、質屋の店先で西日に晒(さら)されていたモノクロ(白黒)テレビを買ってきた。
60年にはカラーテレビ放送が開始、普及し始めていたから、シャープ製14㌅の、か細い4本足に支えられたそれはいかにも旧式で、ウサギの耳のようなアルミ製室内アンテナは軽薄で、画面は気まぐれに歪んでその度に茶の間は動揺した。わが家にテレビがやってきたのは町内でもしんがりで、裕福な一部家庭はカラーで、五輪を観戦したはずである。
大会終了後、小学生たちはこぞって街場の映画館へ引率された。社会見学という名目で映画「東京オリンピック」を観るためだった。
小学校5年生で確たる記憶があるわけではないが、のっけの、巨大な「太陽」のアップシーンには度肝を抜かれた。その「太陽」は工事現場の鉄球と重なり、さらに古ビルを破壊してゆく。五輪を契機に新しい東京、日本再建を意図したとは大人になってからの知識で、その頃はただあんぐり口を開けて眺めていた。
この映画の総監督は市川崑であった。当初は黒沢明が担う予定だったが折り合わず、今井正、今村昌平、新藤兼人らがノミネートされるも最後は市川崑が引き取った。
聖火リレーは、沖縄の「ひめゆりの塔」から広島の「原爆ドーム」を俯瞰(ふかん)し、そのドームの、破壊された壁に巣くった2羽の鳩がランナーを見おろすシーンでこの映画が単なるスポーツ記録映画ではないことを明確に物語る。
「太陽の光はあらゆる生き物の生命の源というか、人間にとって一番の光ですし、平和と平等のシンボルです」と市川崑は、生前のインタビューで語っている。
完成披露試写会後、当時の五輪担当大臣・河野一郎が「記録性を無視したひどい映画」と酷評し、文部大臣・愛知揆一も同調、修整を求めたのは有名な話で、これに対し女優の高峰秀子らが反論、その平和メッセージ性を巡って論議を巻き起こした。
ただ映画が封切られると12億円超の配給収入を稼ぎ、観客は一般750万人、学校動員1600万人(そのうちの一人が私であったわけだが)の2350万人を記録した。
映画の締めくくりもまた太陽がフォーカスされる。字幕スーパーが流れる。
「夜、聖火は太陽に帰った。人類は4年ごとに夢を見る。この創られた平和を夢で終わらせていいのであろうか?」
膨大な数の望遠レンズを投入。選手の一挙手一投足を追い、その内面にこだわったこの作品は「平和と友情」を描く壮大な抒情詩、無類の五輪映画となった。
その「夢」は来年、実現されるのであろうか。パンデミックの最中。人類の「平和」、日常が担保されていれば、の話である。
当時小学校5年生であった。開幕日が近づくと、父親があたふたと商店街の、質屋の店先で西日に晒(さら)されていたモノクロ(白黒)テレビを買ってきた。
60年にはカラーテレビ放送が開始、普及し始めていたから、シャープ製14㌅の、か細い4本足に支えられたそれはいかにも旧式で、ウサギの耳のようなアルミ製室内アンテナは軽薄で、画面は気まぐれに歪んでその度に茶の間は動揺した。わが家にテレビがやってきたのは町内でもしんがりで、裕福な一部家庭はカラーで、五輪を観戦したはずである。
大会終了後、小学生たちはこぞって街場の映画館へ引率された。社会見学という名目で映画「東京オリンピック」を観るためだった。
小学校5年生で確たる記憶があるわけではないが、のっけの、巨大な「太陽」のアップシーンには度肝を抜かれた。その「太陽」は工事現場の鉄球と重なり、さらに古ビルを破壊してゆく。五輪を契機に新しい東京、日本再建を意図したとは大人になってからの知識で、その頃はただあんぐり口を開けて眺めていた。
この映画の総監督は市川崑であった。当初は黒沢明が担う予定だったが折り合わず、今井正、今村昌平、新藤兼人らがノミネートされるも最後は市川崑が引き取った。
聖火リレーは、沖縄の「ひめゆりの塔」から広島の「原爆ドーム」を俯瞰(ふかん)し、そのドームの、破壊された壁に巣くった2羽の鳩がランナーを見おろすシーンでこの映画が単なるスポーツ記録映画ではないことを明確に物語る。
「太陽の光はあらゆる生き物の生命の源というか、人間にとって一番の光ですし、平和と平等のシンボルです」と市川崑は、生前のインタビューで語っている。
完成披露試写会後、当時の五輪担当大臣・河野一郎が「記録性を無視したひどい映画」と酷評し、文部大臣・愛知揆一も同調、修整を求めたのは有名な話で、これに対し女優の高峰秀子らが反論、その平和メッセージ性を巡って論議を巻き起こした。
ただ映画が封切られると12億円超の配給収入を稼ぎ、観客は一般750万人、学校動員1600万人(そのうちの一人が私であったわけだが)の2350万人を記録した。
映画の締めくくりもまた太陽がフォーカスされる。字幕スーパーが流れる。
「夜、聖火は太陽に帰った。人類は4年ごとに夢を見る。この創られた平和を夢で終わらせていいのであろうか?」
膨大な数の望遠レンズを投入。選手の一挙手一投足を追い、その内面にこだわったこの作品は「平和と友情」を描く壮大な抒情詩、無類の五輪映画となった。
その「夢」は来年、実現されるのであろうか。パンデミックの最中。人類の「平和」、日常が担保されていれば、の話である。
(日刊スポーツ I / 2020年10月)
★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで